小さな会社の採用ということで、お金をかけないでできることなどが書かれています。
また、ミスマッチを防ぐ方法なども紹介されています。

『小さな会社の採用 お金をかけなくてもここまでできる!』中谷充宏
目次
第1章 今までの応募書類、面接では「良い人材」は採れない!
第2章 ≪良い人材が集まるツボ①≫ お金はかからない! ネットの新手法
第3章 ≪良い人材が集まるツボ②≫ お金はかからない! アナログの新手法
第4章 面接で「即戦力」を見抜き自社の魅力を伝えるコツ
第5章 法的リスクもこれで安心、「体験会」「有期雇用」で絞り込むポイント
第6章 たった一人でも職場を破壊!「ヤバい人」をブロックする4つの盾
第7章 この「内定者の選び方」「フォローのコツ」で定着率が大幅アップ!
『小さな会社の採用』ここに注目・言葉・名言
「「集まる求人」になるポイント
結論はシンプルです。
応募者が知りたい情報を、正確かつ詳細に載せる。これしかありません。
中小零細企業で「あるある」なのが、たとえば就業時間について。
「9時00分~18時00分(1日8時間)、休憩:12時~13時」と、法定通りの内容を載せたとしましょう。実態がこの記載通りなら問題ありませんが、そういったケースの方が少ないでしょう。
「入社したら残業がどれだけあるのか?休日出勤はあるのか?」といった、応募者が知りたいところまで詳細に載せることが大事です。
「額面通りに載せたが実態は違う(入社してみたら実態が違った)」は絶対NGです。
応募者が知りたいのは、大きく分けて、①職種、②業務内容、③応募資格、④就業時間・休日、⑤給与、⑥転勤の有無、⑦福利厚生・教育制度の7つです。」(p.32-33)
応募者が知りたい情報を、正確かつ詳細に載せる
集まる求人になるポイントは、
応募者が知りたい情報を、正確かつ詳細に載せる
ということです。
まあそうですね。
そして、7つのポイントを詳しく伝えるということです。
内定辞退を防止するには?
「内定辞退を防止するには?
内定辞退は、皆さんもご経験がおありでしょう。
本人の意思で他社に流れるのは防ぎようがありませんが、他社に流れるのは自社のやり方がマズかったからかもしれません。
内定出しして入社するのを心待ちにしていたが辞退された、ということになると、少人数の中小零細企業ゆえにダメージが大きいです。
次に挙げる①②の施策により、内定辞退を見通せるようにしておくべきです。
①内定出しの際に、応募者の本音を聴き出す
②期限を設けて入社承諾書を提出させる
①について、内定を出そうと思っていますが、当社で働く気持ちはありますか?
もしまだ固まっていないなら、どのような要因があるのか、たとえば何が不安、不満なのかなど、率直にお話しいただけませんか?」と、尋ねるのは有効です。内定出しを前提にすると本音を話してくれる可能性が高まります。自社で善処できる内容なら、約束すれば辞退は避けられるでしょう。
入社承諾書は、だいたい2週間以内に提出させることが多い
②について。
中小零細企業ゆえに、こうした書類整備がどうしてもルーズになりがちですが、内定通知書とともに入社承諾書を渡しておき(7章末参照)、「内定を正式に受けるなら、2週間以内にこれを提出してください」と伝えます。2週間経過して提出がなければ次点を繰り上げる、新候補者を探すといった次の対策が打てます。もちろんごの間も、①のようなコミュニケーションを図るのは有効です。」
(p.210-211)
内定辞退に対処
内定を出す前に、どうなのかを相手に聞くということですね。
不満や不安などで対応できることであれば、あらかじめ対応できますし。
また、入社承諾書を出してもらうことで、相手の意思も確認できて、出してこないのであれば、別の人をということにもしやすいですね。
内定辞退がありうる前提で、初めから考えておいて、対処できるようにしておくのが、やはり今の時代には必要なのでしょうね。
取り入れたいと思ったこと
「定着に有効なメンター制のポイント
就業経験がある人であっても、新しい職場環境には簡単にはなじめないものです。
そこでぜひ取り入れてほしいのが、メンター制です。
これは簡単に言うと、直属の上司や先輩とは別の社員が、新入社員の面倒を見ていくという制度です。年齢の近い、社歴が近い先輩社員で、面倒見の良い、話がしやすいタイプの人が適任と言えます。
新入社員にとっては、不安や悩みを気軽に相談でき、新しい職場にフィットするスピードが速くなるメリットが、メンター役を任される先輩社員にはコミュニケーションスキルが向上し、仕事、職場に対する責任感が強くなるメリットがあります。」(p.216)
定着も考えたいとしたら、メンター制度も良さそうですね。
新人にも良いですし、メンター側・先輩にも良いところがありそうです。
あわせて読みたい
『最高の働きがいの創り方』三村真宗。何を共有すると良いか? - ビジネス書をビジネスのチカラに。書評ブログ
こちらは、働きがいを作るために、どんなことをやっているのかといったことが書かれています。
様々な仕組み、施策を行なっているということがわかります。
働きがいを作りたい経営者の方などが読まれると、参考になることが見つかると思います。
『小さな会社の採用お金をかけなくてもここまでできる!』
おすすめ度
★★★★☆
小さな会社の採用ということで、お金をかけずにできることなどが書かれています。
採用を改善したいという方などが読まれると、参考になることが見つかると思います。
おすすめしたい方
採用担当者。
経営者。
今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
応募者が知りたい情報を、正確かつ詳細に載せる
応募者が知りたい情報を、正確かつ詳細に載せていますか?
 メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!
メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!

![小さな会社の採用お金をかけなくてもここまでできる! [ 中谷充宏 ] 小さな会社の採用お金をかけなくてもここまでできる! [ 中谷充宏 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2937/9784798072937_1_3.jpg?_ex=128x128)


![SNSはキーワードが9割 [ 三浦孝偉 ] SNSはキーワードが9割 [ 三浦孝偉 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3262/9784798073262_1_3.jpg?_ex=128x128)



![医者が教える最強の不老術 細胞レベルで若返る食事と習慣のすべて [ マーク・ハイマン ] 医者が教える最強の不老術 細胞レベルで若返る食事と習慣のすべて [ マーク・ハイマン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8863/9784478118863_1_2.jpg?_ex=128x128)



![売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ] 売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3774/9784413233774_1_3.jpg?_ex=128x128)


![幸せな仕事はどこにある 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義 [ 井上 大輔 ] 幸せな仕事はどこにある 本当の「やりたいこと」が見つかるハカセのマーケティング講義 [ 井上 大輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7583/9784492047583_1_2.jpg?_ex=128x128)



![1500社の社長を救った虎の巻 経営の極意 [ 三條 慶八 ] 1500社の社長を救った虎の巻 経営の極意 [ 三條 慶八 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2749/9784866802749_1_2.jpg?_ex=128x128)
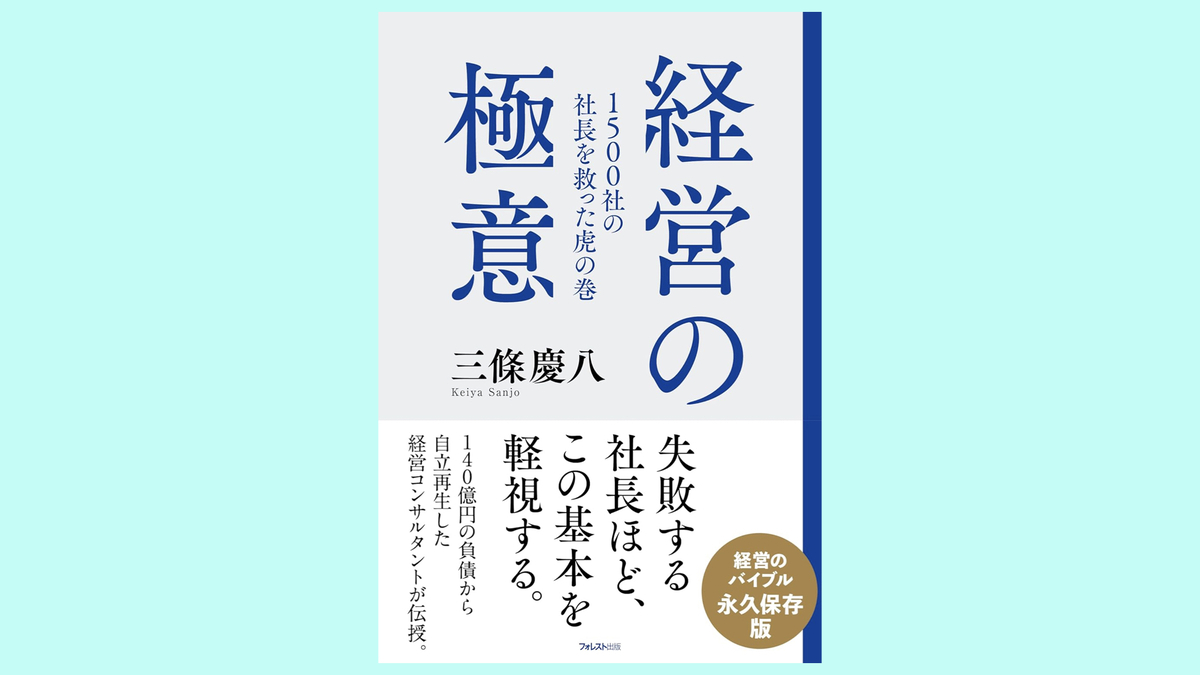

![小さな会社の売れる仕組み [ 久野 高司 ] 小さな会社の売れる仕組み [ 久野 高司 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2893/9784866802893_1_2.jpg?_ex=128x128)
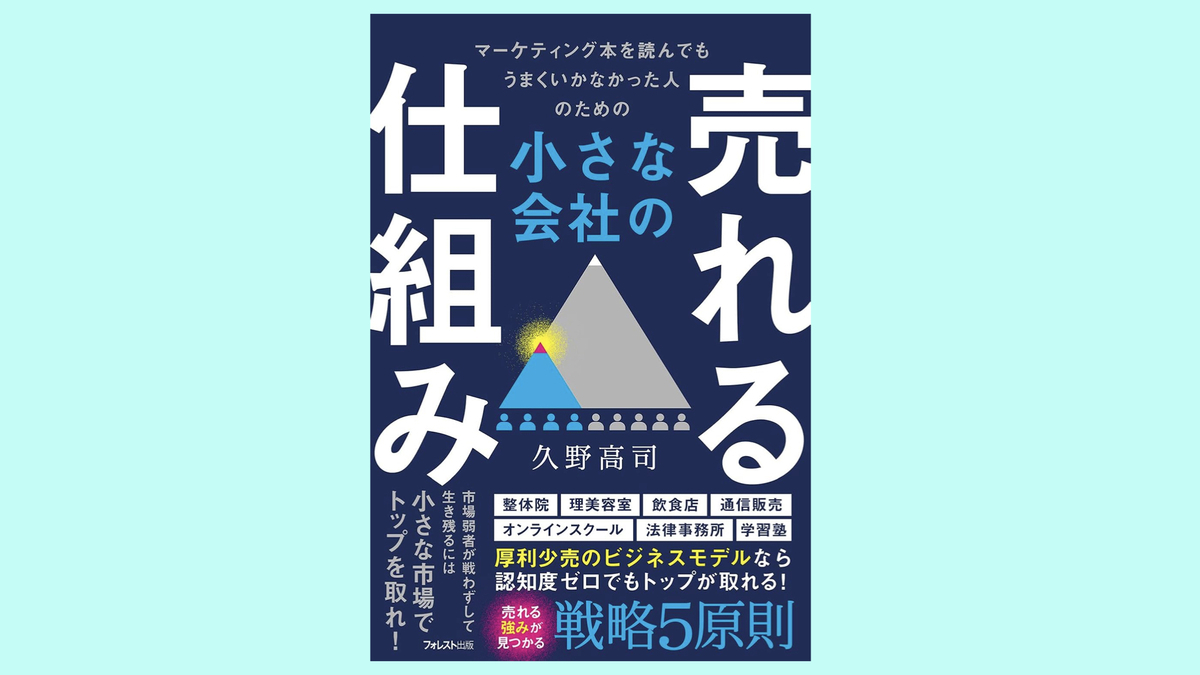


![結局、否定しない人ほどうまくいく [ 吉田幸弘 ] 結局、否定しない人ほどうまくいく [ 吉田幸弘 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4299/9784522454299_1_2.jpg?_ex=128x128)



![セールス・イズ 科学的に「成果をコントロールする」営業術 [ 今井晶也 ] セールス・イズ 科学的に「成果をコントロールする」営業術 [ 今井晶也 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8743/9784594088743_1_2.jpg?_ex=128x128)
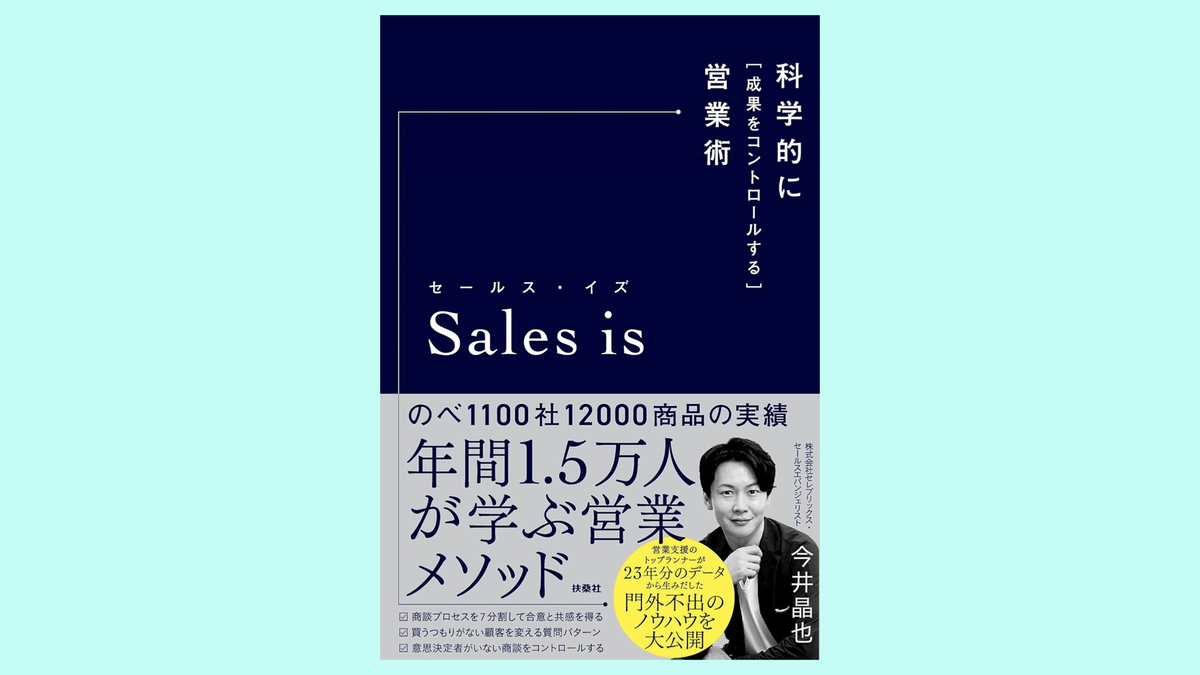


![進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営 [ 酒井 大輔 ] 進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営 [ 酒井 大輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5158/9784296205158_1_4.jpg?_ex=128x128)

