事業計画の極意ということで、事業計画の立て方について書かれています。
ビジョンを実現するために、数字としてどう表現していくか、その方法論などが解説されています。
事業計画の必要性などがわかると思います。

- 『事業計画の極意: 仮説と検証で描く成長ストーリー』木村 義弘
- 『事業計画の極意』のここに注目・言葉・名言
- 事業責任者の本当の仕事
- 取り入れたいと思ったこと
- あわせて読みたい
- 『事業計画の極意: 仮説と検証で描く成長ストーリー』
- 今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
『事業計画の極意: 仮説と検証で描く成長ストーリー』木村 義弘
目次
はじめに
第1章 事業計画に向き合う
第2章 事業計画にとりかかる前に
第3章 事業計画全体を設計する
第4章 トップラインを考える
第5章 コストは方程式
第6章 資金について考える
第7章 【発展】BS・CFの設計
第8章 事業計画を使い倒すPDCA
第9章 事業計画で描く経営の未来
おわりに
『事業計画の極意』のここに注目・言葉・名言
「事業計画の役割
さて、その問いについて考えてほしい。
事業計画とは〇〇のツールである。〇〇に当てはまる言葉は何か?
では、事業計画はどんな目的・機能を担うのだろうか。
問いに対し、私は「4つの顔がある」と説明する。言い換えれば事業アイデア
整理、コミュニケーション、実行支援、仮説検証という4つの目的、機能がある。」
(p.7)
事業計画の役割
事業計画の役割は、
事業アイデア整理
コミュニケーション
実行支援
仮説検証
こういった4つの役割があるということです。
事業計画があると、こういったことが進めやすい。
逆に、事業計画がないと、これらを進めにくくなるということですね。
事業責任者の本当の仕事
「私は、事業責任者・経営者にとって本当に大切な仕事は、収益構造を構造化していくことではなく、構造化したKPIツリーに基づき、「何がKPI (=Key Pertormance Indicator)なのかを見極めること」だと考えている。
自社が行う事業にとって,その瞬間のKPIが何か。これは、KPIが事業ステージによって変わっていくことを示唆する。
Saas・サブスクリプションビジネスであれば、最初は「新規契約アカウント数」がKPIとなる。一定の期間ビジネスが進んできたときには、解約を止めるために、解約率
をKPIとして設定する。解約率が落ち着いてきたら、ARPU (Averaged Revenue Per User, 1顧客当たりの平均収益)としてアップセルをどこまで伸ばせるか考える。
どのタイミングでKPIが変わるかの判断を含めて、KPIの見極めこそが事業責任者・経営者の重要な仕事なのだ。」
(p.151)
何がKPI (=Key Pertormance Indicator)なのかを見極めること
事業責任者の本当の仕事は、何がKPIなのかを見極めることだそうです。
重要なポイントは何か。
ここを決めて、改善するようにしていくのが、事業責任者、経営者の仕事だということです。
取り入れたいと思ったこと
「市場規感を踏まえて、成長シナリオを考えたい。自身の事業をどう伸ばしていくかについては大きく2つがある。1顧客を広げる、もしくは2単価を上げるかだ。なお、単価を上げるには、単純に「商品単価を上げる」より、おカネのもらい方を増やすと考えた方がよいであろう。」(p.164)
顧客を広げる、単価を上げる
考えたいですね。
あわせて読みたい
こちらは、経営のポイントなどについて、Q&A形式で書かれています。
経営のヒントなどを知りたい方が読まれると、参考になることが見つかると思います。
『事業計画の極意: 仮説と検証で描く成長ストーリー』
おすすめ度
★★★★☆
事業計画の立て方などが書かれています。
事業計画を立てる意義などがわかると思います。
起業家や経営者の方が読まれると、参考になるはずです。
おすすめしたい方
経営者。
起業家。
今日の読書「ビジネス書をチカラに!」
事業計画の役割は、
・事業アイデア整理
・コミュニケーション
・実行支援
・仮説検証
事業計画を立てていますか?
 メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!
メルマガで読みたい方は、ぜひご登録を!

![事業計画の極意 仮説と検証で描く成長ストーリー [ 木村 義弘 ] 事業計画の極意 仮説と検証で描く成長ストーリー [ 木村 義弘 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5019/9784502515019_1_4.jpg?_ex=128x128)


![「あたりまえ」のつくり方 ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書 [ 嶋浩一郎 ] 「あたりまえ」のつくり方 ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書 [ 嶋浩一郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3324/9784910063324_1_2.jpg?_ex=128x128)
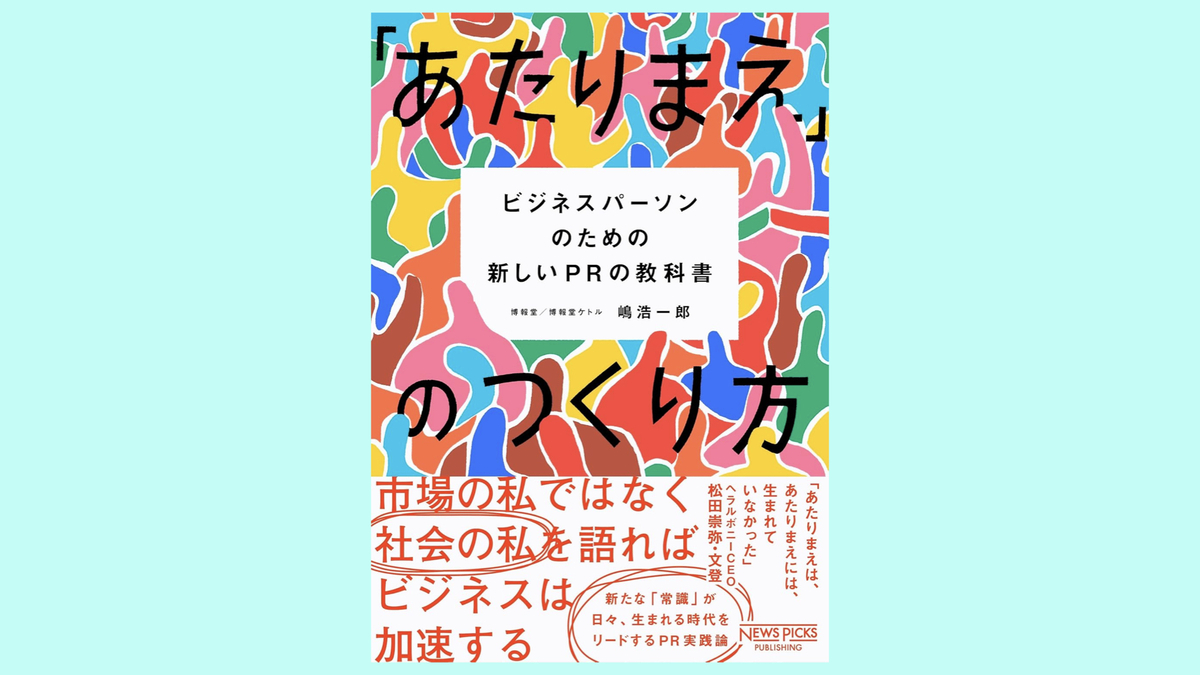


![キーエンス流 性弱説経営 人は善でも悪でもなく弱いものだと考えてみる [ 高杉 康成 ] キーエンス流 性弱説経営 人は善でも悪でもなく弱いものだと考えてみる [ 高杉 康成 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6414/9784296206414_1_37.jpg?_ex=128x128)
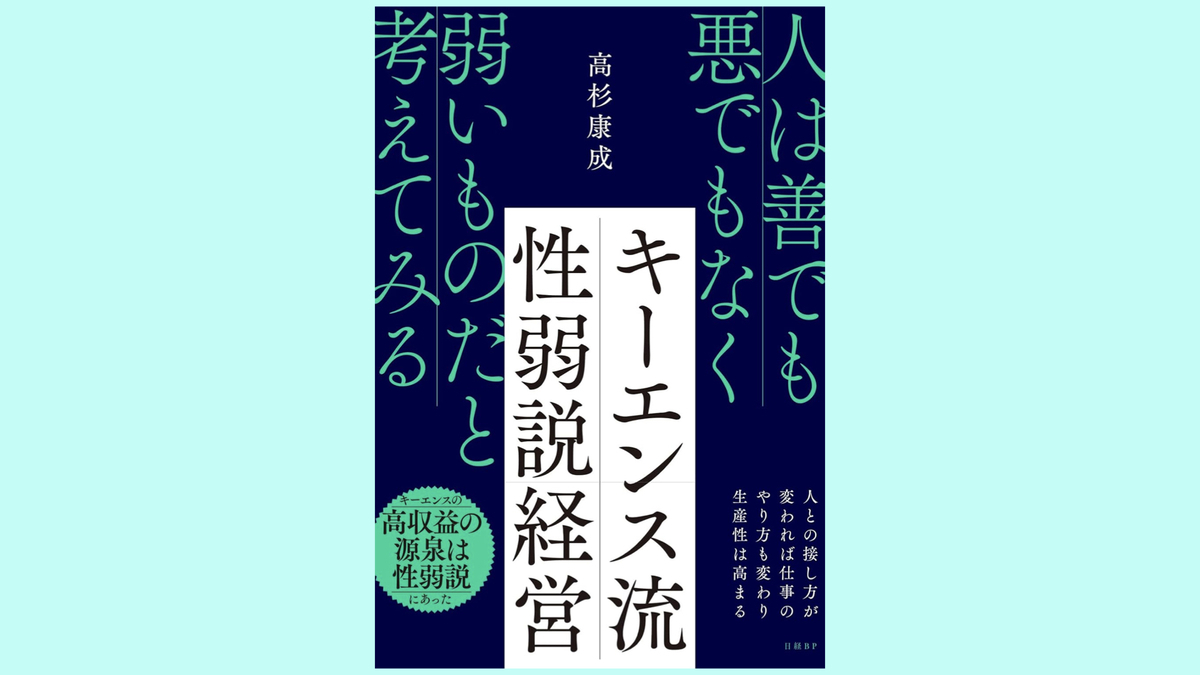


![ユニクロの仕組み化 [ 宇佐美 潤祐 ] ユニクロの仕組み化 [ 宇佐美 潤祐 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8246/9784815628246_1_5.jpg?_ex=128x128)
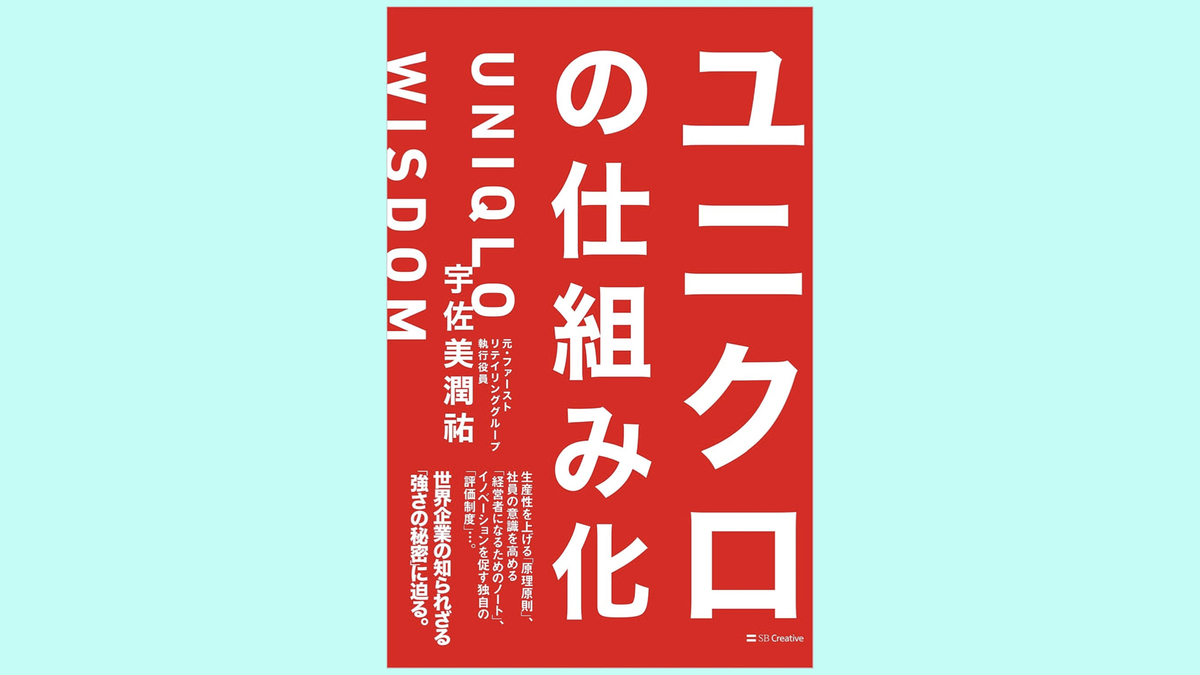
![経営者になるためのノート ([テキスト]) 経営者になるためのノート ([テキスト])](https://m.media-amazon.com/images/I/21OIhMFu5cS._SL500_.jpg)

![小さな会社の採用お金をかけなくてもここまでできる! [ 中谷充宏 ] 小さな会社の採用お金をかけなくてもここまでできる! [ 中谷充宏 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2937/9784798072937_1_3.jpg?_ex=128x128)



![売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ] 売れる「値上げ」 [ 深井賢一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3774/9784413233774_1_3.jpg?_ex=128x128)



![1500社の社長を救った虎の巻 経営の極意 [ 三條 慶八 ] 1500社の社長を救った虎の巻 経営の極意 [ 三條 慶八 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2749/9784866802749_1_2.jpg?_ex=128x128)
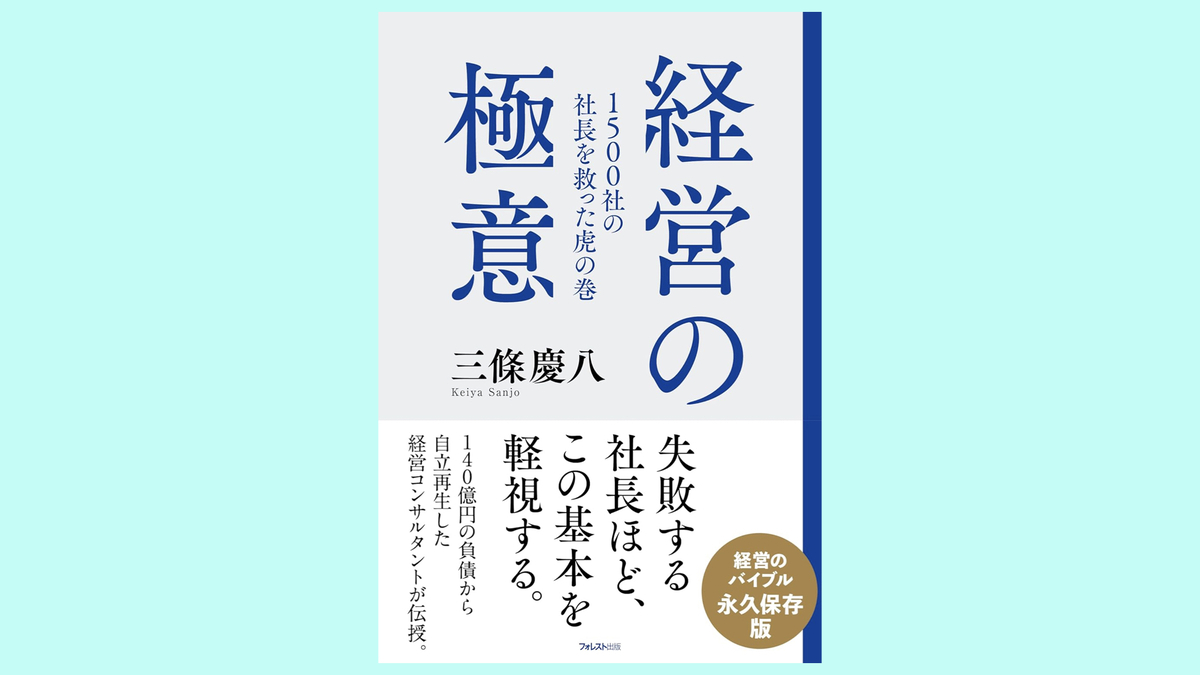


![進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営 [ 酒井 大輔 ] 進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営 [ 酒井 大輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5158/9784296205158_1_4.jpg?_ex=128x128)



![サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術 [ 堀埜一成 ] サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術 [ 堀埜一成 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0395/9784799330395_1_4.jpg?_ex=128x128)
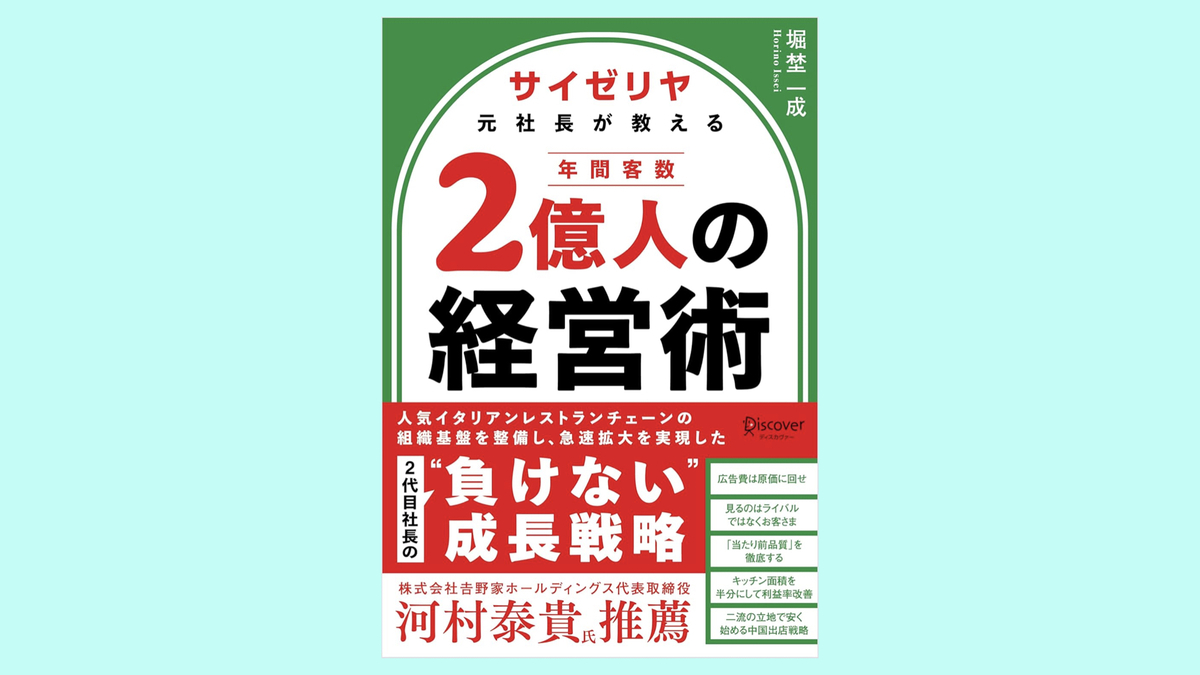

![愛される企業 社員も顧客も投資家も幸せにして、成長し続ける組織の条件 [ ラジェンドラ・シソーディア ] 愛される企業 社員も顧客も投資家も幸せにして、成長し続ける組織の条件 [ ラジェンドラ・シソーディア ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1002/9784296001002_1_3.jpg?_ex=128x128)

